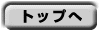
中高 美術(過去問題)
【1】次の各文は、版画の技法の例について述べたものである。それぞれの技法名として適当なものをあとからそれぞれ一つ選び、記号で答えよ。
(1)木を輪切りにした板を版材として用い、ツゲなどの堅い木を版木として使用する。版は、主にビュランで緻密に彫り込み、油性のインクをのせてプレス機で刷る。作家によってはプレス機を使わずにバレンで摺ったり、スプーンの背でこすって細かい調子を摺り出したりする。
(2)凹凸をつけずに、油が水をはじくという原理を利用した版画の技法。図柄を油分を含んだ描画材で石版等に描き、化学溶剤で処理後、版面を湿らせて、油性のインクをローラーなどにつけて版の上にのせると、湿った部分はインクをはじき、描画材で描いた部分にのみインクが付着する。
(3)刃先がV字型に鋭くとがったビュランで銅版等金属に直接図柄を彫り込む技法。浮彫状の模様を施す彫金の技術から生まれた。シャープで硬質な線が特徴である。
(4)櫛目上の刃のついたロッカー(ベルソー)を銅版面のあらゆる方向に動かして、無数の細かい傷やささくれをつくり、版に目立てをする。スクレイパーで版上のささくれを削り取ったり、バニッシャーで磨いたりしてグレーや白のトーンをつくり出すことで図柄を表す。
(5)孔版画の技法で、枠に絹などの布を張り、様々な方法で目止めをしてインクが出ない部分をつくり、裏側からインクを押し出して刷る。商品のラベルやポスターなど実用的な印刷物の技法として活用されてきたが、1960年代のポップ・アートにおいては主要な表現媒体の一つとなった。
| (ア)エッチング (イ)ドライポイント (ウ)リトグラフ (エ)板目木版 (オ)木口木版 (カ)シルクスクリーン (キ)エングレーヴィング (ク)メゾチント (ケ)アクアチント |
| [平成21年度 川崎市教員採用試験実施問題(中学)] |
【2】次の文章を読んで、あとの各問いに答えよ。
映画の静と動ということを書いたが、絵巻物にも同じように、この二つの美学をそれぞれ代表するような傑作がある。たとえば( ア )に描かれた『( イ )絵巻』と『( ウ )絵巻』。
『(イ)絵巻』は貴族の生活を描いた文学作品を、絵画化したものだ。(ア)の貴族には、落ち着きや謙虚などという「静」の美意識が尊ばれた。その作品を描いた『(イ)絵巻』でも「静」の美が結晶している。人物の描写、とくに「( エ )」といわれる顔の描き方は、表情という顔の「動き」をおさえて、しかしその奥にかすかに見える心理を映している。まさに「静」の美の典型だ。「静」の絵巻に対して、「動」のもつ生き生きした躍動感を描いているのが『(ウ)絵巻』だ。庶民の、荒っぽいがたくましい生活などを描いて『(イ)絵巻』の美とは別の、もう一つの絵巻のあり方を見せてくれている。 (布施英利著『美術館には脳がある』による)
(1)( )にあてはまる語句を答えよ。ただし、(ア)には時代を、そのほかには適当な語句を答えよ。
(2)絵巻物の表現で特徴的なものとはどのようなものか、答えよ。
(3)美術Ⅰの鑑賞で、日本の伝統的な美術をどのように扱うことが必要か、答えよ。
| [平成21年度 熊本県教員採用試験実施問題(高校)] |
<2008/11/28アップ分>
【1】次の文章は、近代以降のある西洋美術の運動について述べたものである。各運動名を答えるとともに、あとの人物名の中から関係の深い画家を2名ずつ選び、記号で答えよ。
(1)第一次世界大戦後、ダダに続いて登場した幻想絵画の潮流で、夢や無意識・非合理の世界を表現することにより、新しい価値を創造しようとした。作品制作にあたって「フロッタージュ」や「デカルコマニー」などの新しい技法を用いたことも忘れてはならない。
(2)19世紀後半の世紀末芸術運動のひとつで、反写実主義的な性質をもち、神秘的なテーマを宗教的・観念的に表現しようとした。表現主義の元祖とも呼ばれるエドヴァルト・ムンクも、この運動に取り組んだ一人である。
| (ア) ギュスターヴ・モロー (イ) サルバドール・ダリ (ウ) ジョルジオ・デ・キリコ (エ) ポール・ゴーギャン (オ) オデュロン・ルドン (カ) アンドリュー・ワイエス |
| [平成20年度 佐賀県教員採用試験実施問題(中学美術)] |
【2】美術史に関する、次の各問いに答えよ。
(1)( )にあてはまる語句を答えよ。
A.室町時代を特色づける美術に建築と庭園がある。建築は今日の住宅につながる( ア )が誕生し、また禅宗の発展から禅宗寺院には( イ )などこの時代の象徴的な庭園が造られた。
B.江戸時代の( ウ )文化を代表する画家に( エ )がいる。俵屋宗達の影響を受け大和絵に独自の画風を開いた。この派の画風を琳派と呼ぶ。代表作に「紅梅白梅図屏風」がある。
C.明治時代、行き過ぎた欧風化に対する反動が起こり、日本の伝統美術の再評価がされるようになる。1878年来朝した( オ )は日本美術の優秀性を説き、岡倉天心とともに古美術の保存に努め、新しい日本画の創造を主張した。
(2)次の語句を説明せよ。
A.バロック B.シュルレアリスム
| [平成20年度 宮崎県教員採用試験実施問題(高校美術)] |
<2008/4/4アップ分>
【1】次の各文は西洋美術における様式や運動について述べたものである。a~hの名称との組合せとして正しいものをあとから一つ選び、記号で答えよ。
(1)19世紀末から20世紀初頭にヨーロッパを中心に展開した運動。装飾や工芸の価値を芸術の域まで高めようとし、西洋美術の伝統的なヒエラルキーを問い直した。様式的には自然をモチーフとした曲線的で有機的な形態を特徴とする。
(2)12世紀前半から15世紀末頃、主にアルプス以北で発展した建築・美術様式。尖塔アーチや飛梁など構造要素の革新によって大聖堂など巨大建築が可能になり、建築枠にとらわれない丸彫り彫刻や絵画は優美で自然主義的傾向が強い。
(3)16世紀末のイタリアから発し、17世紀のヨーロッパと中南米のスペイン・ポルトガル植民地で展開した美術。盛期や様式に地域差はあるが、過剰な装飾性、感情に訴える劇的な動きや明暗の表現などを特徴とする。
(4)1710年から1760年代にかけてフランスからヨーロッパに波及した美術。本来は、左右非対称、曲線の多用、繊細さや軽妙さへの好みなどを特徴とする装飾様式を指したが、現在ではこの時代の美術全般に適用される。
(5)修道院を中心に11世紀から12世紀にかけて西欧各地で発展した建築・美術様式。地方色が強く多様で、重厚な外観と暗く静謐な内部空間をもち、建築枠の制約を受けた彫刻や色鮮やかな壁画は平面的だが生命力に溢れる。
| a ロマネスク様式 b ロマン主義 c アール・ヌーボー d 古典主義 e ロココ美術 f ビザンティン美術 g ゴシック美術 h バロック美術 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| (ア) | f | g | d | c | a |
| (イ) | a | e | f | b | d |
| (ウ) | c | h | f | e | g |
| (エ) | c | g | h | e | a |
| (オ) | b | a | h | c | e |
| [平成19年度 岐阜県教員採用試験実施問題(中学)] |
【2】デザインに関する次の各問いに答えよ。
(1)「溝引き」とはどのような技法か。簡潔に説明せよ。
(2)日本工業規格(JIS)によるB判の用紙は、長辺を半分に折り曲げると相似形になる。この短辺を1とした場合、長辺の比率はどのようになるか、答えよ。
(3)次の文章は混色について述べたものである。( )にあてはまる語句を答えよ。
色料の混色や( ア )によって得られる色は、「色料の三原色」の混色のように、元の色より( イ )が低くなる。このような混色を( ウ )混色という。これに対し、色光の場合は、「色光の三原色」の混色のように、混色によってできる色の(イ)が高くなる。このような混色を( エ )混色という。
(4)明朝体の特徴を、ゴシック体と比較しながら二つ説明せよ。
(5)「余」の字を、明朝体で描け。
| [平成20年度 鹿児島県教員採用試験実施問題(中高美術)] |
<2007/11/9アップ分>
【1】中学校学習指導要領及び中学校学習指導要領解説美術編において述べられている美術科の目標及び内容について、次の各問いに答えよ。
(1)平成14年改訂前までの美術の目標は「能力、心情」という順で設定されていたが、平成14年の改訂で「心情、感性、能力」という順に改善されている。この改善の趣旨を簡潔に述べよ。
(2)次の文は、中学校学習指導要領の各学年の目標及び内容のうち、第1学年に示されているものである。( )にあてはまる語句を漢字2字でそれぞれ書け。
| 描画における形や( A )の表し方、彫刻などにおける( B )としてのものの見方や形体の表し方、( C )に応じた材料や( D )の生かし方などの基礎的技能を身に付けること。 |
(3)中学校で実施する彫刻などの表現方法を、表現の仕方や材料などで分けると塑造、彫造、その他の3つに分けることができる。それぞれどのような表現方法か。「表現方法」という言葉につながるように述べよ。
| [平成19年度 島根県教員採用試験実施問題(中学美術)] |
【2】次の文章は、色の三要素(三属性)に関する記述である。( )にあてはまる適切な語句を書け。
(1)「暖かい、熱い」や「寒い、冷たい」という感覚をいだく色は、色の三要素(三属性)の中の( )に影響される。
(2)「軽い」や「重い」という感覚をいだく色は、色の三要素(三属性)の中の( )に影響される。
(3)「強い、硬い」や「弱い、柔らかい」という感覚をいだく色は、色の三要素(三属性)の中の( )に影響される。
| [平成19年度 長野県教員採用試験実施問題(高校美術)] |
<2007/3/23アップ分>
【1】次の各問いに答えよ。
(1)鎌倉時代以降、今もなお陶器づくりが盛んに行われている代表的な6つの窯業地を「六古窯」という。その「六古窯」ではない窯業地はどこか、次からあてはまらないものを一つ選び、記号で答えよ。
(ア)備前 (イ)丹波 (ウ)常滑 (エ)瀬戸 (オ)越前 (カ)有田 (キ)信楽
(2)第一次世界大戦に対し、既成の権威に対する反抗と一切のものから自由になることを旗印に、世界各地に広がった芸術家たちの反抗的運動をダダイズムというが、その中心となって活躍した作家は誰か。次から適当なものを一つ選び、記号で答えよ。
(ア)マティス (イ)ロスコ (ウ)ド・スタール (エ)デュシャン (オ)チリーダ
(3)バロック美術に最も関係の深いものはどれか、次のAから適当なものを一つ選び、記号で答えよ。また、バロック美術とは関係のない作家をあとのBから適当なものを一つ選び、記号で答えよ。
A.(ア)貝殻型の装飾モチーフ (イ)ゆがんだ真珠 (ウ)写実的 (エ)アカデミズム (オ)非対称、優雅さ
B.(ア)ルーベンス (イ)レンブラント (ウ)ベラスケス (エ)ベルニーニ (オ)ゴヤ
(4)次のAの(ア)~(オ)を焼き物の制作過程順に並べよ。また、素焼きの温度は何℃くらいか、あとのBから適当なものを一つ選び、記号で答えよ。
A.(ア)施釉 (イ)乾燥 (ウ)成形 (エ)素焼き (オ)土ねり (カ)本焼き
B.(ア)400℃ (イ)600℃ (ウ)800℃ (エ)1000℃
| [平成19年度 長崎県教員採用試験実施問題(中学美術)] |
【2】次は高等学校の美術Ⅰ「A表現(1)絵画・彫刻」の評価基準の具体例である。これらを関心・意欲・態度にあたるものをA、芸術的な感受や表現の工夫にあたるものをB、創造的な表現の技能にあたるものをCとして観点別に分類せよ。
(1)美に対する感動や情感、自己の考えや夢を基に、主体的に表現しようとする。
(2)スケッチやデッサンを繰り返し行い、対象の特徴をつかむ力を身に付ける。
(3)想像を働かせてイメージを湧出させ、主題を生成する。
(4)表現したい主題を自ら生成するために、自らの内面に働きかけている。
(5)表現の主題を深めるために、表現の過程でも試行錯誤によってさらに練り高めようとする。
(6)絵画や彫刻における材料の特性や用具の使い方などを理解し、効果的に活用する。
(7)表現の幅を広げ、自己の意図に合った表現方法を創意工夫する。
(8)形や色彩によって生まれる感情や美しさなど表現効果を考えた構成を試みる。
(9)色彩と形体、面や質感、量感、空間、均衡や動勢などの造形要素を理解し、表現の構想を練る。
(10)表現方法の特性による表現効果の違いに気付き、意図に応じて創造的に活用する。
| [平成19年度 大阪府教員採用試験実施問題(高校美術)] |